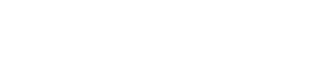祖父 と孫 とそれぞれの思い
――計画通り。
世界樹にハッキングを仕掛け、最奥にフラグを残したことで匠海は司法取引を行い、世界樹のカウンターハッカーとして契約することとなった。
目的はただ一つ。
あの
トラックの運航会社のサーバにあったログは
本来なら、同じく
しかし、彼はその封印を破ることができなかった。
頼みの綱の
それが目の前で和美を喪ったトラウマであるということは彼も理解していた。
理解していたが故に、「エクスカリバーに拒まれた」のだと、思っていた。
――あの時、俺が動けていれば。
あの時自分が和美を守ることができていれば、このようなことにはならなかった。
それにより自分がこの世にいなかったとしても、彼女さえ生きていればそれでよかったのだ、と匠海は思っていた。
だが、起こってしまったことを今更悔やんでも仕方がない。
だから、匠海はログのコピーが保管されている世界樹を攻めた。
セキュリティは運行会社のサーバに比べて数倍は堅い。しかし、堅いが故に魔法使いも運行会社のマスタデータ以上の改ざんはできていないだろう。
今回敢えて逮捕されたのは世界樹の深層に到達できるほどの
そしてその思惑通り、世界樹は司法取引を持ち掛けてきた。
曰く、カウンターハッカーとしてその実力を伸ばせ、と。
留置担当官の案内で出口に向かう匠海は今後どうするか、とふと考えた。
もちろん、カウンターハッカーとして世界樹に行くことは確定している。
考えたのはその後、どうするか、だった。
目的を果たしたあと、自分はどうするのだろうか。
――後を追うのか?
それも良いもしれない、と、ふと思う。
今の自分はただ和美の無念を晴らしたいだけだ。それ以外に何も望まない。
それなら全てが終わったら後を追っても。
「……バカだな、俺は」
――そんなことをして、和美が喜ぶと思うのか?
そんな考えが浮かび上がる。
あいつならきっと、全力で追い返した挙句あの世の入り口に塩を撒くんだろうな、その方があいつらしい、とさえ思う。
それでも、自分は和美のいないこの世界で生きていくのは辛いのだと。
そこまで考えたところでエントランスに到着する。
ここまで案内してくれた留置担当官に一礼し、匠海は外に出た。
今まで薄暗い留置所にいたため外の光が眩しい。
匠海が思わず目を細めて手を目の上に上げた時、思わぬところから彼を呼ぶ声が投げかけられる。
「匠海、やっと来たか」
一瞬、何が起こったのかを理解できずに手を下ろしてキョロキョロする匠海。
「こっちだ、もう儂のことも忘れたのか」
「……ジジイ……?」
声の方向に視線を投げると派手なアロハシャツを着た老人が目に入った。
車の前で自分に向かって手を振る老人――
「そろそろ出てくるんじゃないかと思ったが、案外遅かったな」
「ジジイ、どうして」
白狼の前に移動し、匠海が尋ねる。
んなもん、と白狼が笑う。
「お前が司法取引することくらい読めてるわ。だったら時間的にそろそろだろう、とな」
とりあえず乗れ、と白狼が助手席のドアを開ける。
「……いや、俺は」
込み上げてくる吐き気を悟られぬよう考えるかのように口元に手を遣り、匠海が断ろうとする。
最近の自動車は自動運転のレベル4に到達していることもあり、一応運転席はあるものの自動運転となっている。
だが、その自動運転システムがハッキングされ、あの事故は発生した。
それ以来、匠海は同乗者が誰であろうが自動車――バスやタクシーを含む――には乗っていない。ある程度の距離の移動が必要となった場合は鉄道を利用している。それ以外は大抵徒歩か電動スクーターに乗る。
怖いのだ。自動運転の自動車が。
自分が乗っている時にハッキングされれば。
それにより、悲しむ人間が現れることが怖かった。
だから、同乗者がたとえハッキングに強い白狼であっても車には乗りたくない。
白狼の腕を信じていないわけではない。あの和美が自分の後任として託してきたし彼の実力は嫌というほど思い知らされている。
それでも、万が一を考えると恐怖で足がすくむ。
ふむ、と白狼が呟く。
「重症だな」
「……気づいてたのか」
「パトカーのクリーニング代の請求がうちに来たんだが」
そうだった。
逮捕されてパトカーに乗せられた時、乗りたくなくて暴れて公務執行妨害が付いた上にパトカー内で吐いていたのだった、と匠海は思い出す。
その時に身元引受人として唯一の家族である白狼を選んでいたのだ、当然、そうなるだろう。
すまなかった、費用は後で返すと告げ、匠海は歩き出そうとした。
「いや折角迎えにきたんだから乗れよ」
「嫌だ」
キッパリと断り、匠海が歩き出す。
その腕を白狼が掴んだ。
「逃げるのか?」
いつになく強い口調の白狼。
その手を振り解くこともできず、匠海は白狼を見た。
「ジジイ、何を」
「とりあえず、乗れ」
そう言いながら白狼は強引に匠海を助手席に押し込んだ。
「ジジイ……っく、」
込み上げる吐き気に抵抗することもできず、匠海が口を押さえる。
「吐くなら袋はそこだ、使え」
エチケット袋の場所だけ教え、白狼が無情にも車を発進させる。
ちらり、と横目で見て症状は吐き気のみで過呼吸は起こしていないなと判断する。
袋を握りしめ、肩で息をする匠海に白狼は声をかけた。
「
「……ジジイ、てめぇには……っ」
息も切れ切れに匠海がそれを拒絶する。
「ジジイに、俺の気持ちが分かって、たまるか」
「ああ、分からんな」
腕を組み、白狼が即答する。
「身内とは言え他人の感情なんて分かってたまるか。んなもん気持ち悪いだけだ」
自分の感情くらい自分で抱えろ、と冷たく言い、白狼は口を閉ざした。
暫く、吐くまいと苦しげに呻く匠海の息遣いだけが車内に響く。
それも徐々に治まり、匠海はぐったりとシートにもたれかかった。
「ジジイ……」
恨めしそうな声が白狼に投げかけられる。
「落ち着いたか?」
冷静な白狼の声。
その声に、匠海も漸く落ち着きを取り戻す。
「ああ、ジジイ、すまない」
息遣いだけはまだ荒いが、気持ち的には落ち着いた匠海が白狼を見る。
「でもなんで迎えに来た」
「身元引受人だからに決まっとるだろうが」
白狼の言葉に匠海がいや、違うと首を振る。
「それだけの理由で動く人間じゃないだろ、ジジイは。何か思惑があるんじゃないのか」
それは、魔術師としての勘。
魔術師としてハッキングを繰り返してきたがゆえに培われてきた勘が、白狼がただ迎えにくるためだけに来たわけではないと囁いている。
白狼がはは、バレたか、と笑う。
「勘だけはいっちょ前になりおって。その通りだ」
ハッキングの腕はまだまだだが、と続けつつも白狼は真顔になり匠海を見た。
「……世界樹に行くのか」
「……ああ、」
匠海が頷く。
あの事故から数ヶ月、漸く手が届きそうなのだ。
もし、それを止めるというのならたとえ祖父であったとしても――
「止めはせんよ。
「……ジジイ、」
思いの外あっさりと白狼は匠海の世界樹行きを受け入れていた。
お前には無理だ、断って再収監されやがれと言われることを想定していた匠海には少々意外な白狼の発言。
意外そうな顔をしていた匠海に白狼があのな、と抗議する。
「お前のハッキングはまだまだとは言え世界には通用するレベルだからな。そうでなければ世界樹が司法取引を持ちかけることもないだろう」
「……」
自信を持て、匠海、と白狼が続ける。
「お前には復讐する権利がある」
「……っ!」
匠海が思わず体を起こして白狼を見る。
「ジジイ、今……」
「あぁ? どうせ儂が言わずとも復讐するつもりだったんだろう? 世間は『復讐は何も生まない』とか言うだろうがんなもん復讐される側の都合のいい言い分だ。それに正直なところ、儂も腹が立っている」
もし、匠海が復讐を望まなければ自分が手を下す、白狼の言葉はその宣言にすら聞こえる。
ただ、本人が復讐を望むのなら自分は敢えて静観するのだ、そう言いたいのだと匠海は感じた。
「……そうだな」
ジジイの思っている復讐に当たるかどうかは分からないが、と付け加え、匠海が再びシートに身を埋める。
乗った直後の猛烈な吐き気は治まったが気分が悪いのは変わらない。
ちら、と、窓の外に視線を投げ、匠海は口を開いた。
「ジジイはぬるいと思うかもしれないが
「その後はどうするつもりだ?」
その言葉が飛んできた瞬間、匠海の心臓が跳ね上がる。
まさに留置所を出る際に自分が考えていたこと、それをまさか見透かされていたとは。
「……考えてない」
少しの沈黙の後、匠海が呟くように答える。
その言葉に、白狼は、
「嘘だな」
そう、切り捨てた。
「……つまらん男に育ったな、匠海」
「何を」
「愛に殉じるとかきょうび流行らんぞ」
全てお見通しだ、と白狼が呟く。
「儂を置いて逝く気か」
「なんでジジイの心配して生きなきゃいけないんだよ」
それもそうだな、と白狼が頷く。
「和美さんが喜ばんだろうに」
それが、白狼の素直な気持ちだった。
匠海が和美を追って自殺しようともそれは自分には何の関係もない。
匠海にとっては自分はただ一人の身内かもしれないが白狼にはまだ他にも頼れる親類はいる。
だから匠海に「死ぬな」とストレートに言う気はなかった。
それでも、どこかで生きてほしいという思いだけはある。
それは祖父としての思いではなく、一人の友として、そして世界の闇を払う
せっかく
巣立ちしたての雛鳥のような危うさはあったものの、
できれば、これからも仲間として歩きたいという、その思いは伝えたかったが今伝えても届かないだろう。
そう考えると犯人が見つからないことを祈りたくもなる。
匠海が犯人を見つけ、彼の言う「復讐」を遂げれば全てが終わってしまうから。
沈黙が車内を満たす。
「……ジジイ、悪いな」
不意に、匠海が謝罪した。
「こんな不甲斐ない孫で」
白狼が小さくため息を吐く。
その決意は変わらないのかと。
「分かってる、和美が
「皆まで言うな」
白狼が匠海の言葉を遮る。
「それがお前の決断なら儂に止める権利はない。ただ、それを望ましいと思っていない人間もいることだけは覚えとけよ」
「ジジイ、」
まるで、今まで何人もの同じような立場の人間を見送ってきたかのような白狼の言葉。
実際、自分よりは長く生きているからそんなこともあったのだろうと思いつつも匠海は少し胸が締め付けられるような感覚を覚えた。
それが罪悪感なのだとすぐに気づくが、そんなものは要らないとばかりにそっと押し潰す。
「ま、今はそう決めていても目的を果たす頃に考えが変わることもある。新しい出会いだって向こうならあるだろう」
「向こう?」
白狼の言葉に匠海が怪訝そうな顔をする。
その匠海の顔に、白狼はがば、とシートから体を浮かせた。
「匠海、お前、分かってないのか?!」
「何を」
白狼の言葉の意図が読めず、匠海が首を傾げる。
はぁ、と白狼が額に手を当てる。
「お前、世界樹に行くと言ったよな?」
「ああ、」
「それ、アメリカだぞ」
数秒の沈黙。
あああああ、と匠海が車内で頭を抱えて絶叫した。
「そうだった!
気づいてなかったんかーい! と白狼がツッコむ。
「いくら量子通信で世界中の情報がリアルタイムで手に入るからってお前、考えてなさすぎだろ!」
「いやアメリカにあるのは知ってたぞ! ただ実感がなかっただけだ!」
ひとしきり怒鳴り合い、それから二人はふぅ、とシートに体を埋める。
「……アメリカか……」
「おい、そんなので大丈夫か? 就労ビザの取り方とか分かるか?」
多分、と匠海が呟く。
「不安しかねぇ……」
白狼が心配そうに呟く。
「ううむ、こうなったら儂が……」
「ジジイは余計な手出しするな」
とは言ったものの今回申請する就労ビザどうなるんだ、確か専門職ならH-1Bだよな、だがカウンターハッカーって特殊技術者の可能性もあるよな、そうなるとL-1Bの可能性も……と、咄嗟に検索しつつ匠海が唸る。
「匠海、言っとくが就労ビザは滞在期間決まってるからな」
「それはもちろん」
白狼の言葉に、今検索してるから分かってると匠海が答える。
ところが白狼はそれに対し、
「最長六年でケリを付ける気か? いや六年でケリがつくと思ってんのか?」
と、尋ねてきた。
「は?」
それだけ時間があれば十分だろう、と匠海が反論する。
「……まぁ、お前の実力ならそれだけあれば十分か。つまり、お前は儂に向かって生きてあと六年だと宣言する気か」
「それは」
「……一応、
もし、匠海の気が変われば。
匠海の性格を考えると彼が一度決めたことを覆すことはそうそうない、とは思う。
だが、もし。万一、彼の決意を覆すような何かが起これば。
そんなことを期待してしまう。
少し俯き、匠海が沈黙する。
それに対し、何かを言うこともなく、白狼が見守る。
「……ジジイ、ありがとう」
小さく頷き、匠海が小声で呟いた。
「どういたしまして」
何故か照れ臭そうに、白狼は視線を窓の外に投げて呟いた。
◆◇◆ ◆◇◆
空港で、保安検査を終えた匠海を白狼が見送る。
あれから数か月の時間は要したものの、匠海は漸くアメリカ行きの準備を終え、出発することとなった。
「寂しくなるな」
白狼が率直な思いを匠海に告げる。
彼としては匠海が幼いころから、大学に入るまでは共に過ごしていた家族だった。
匠海が家を出てからもそれで縁が切れたわけではなく、なんだかんだと楽しい日々を過ごしていた。
そんな匠海が自分の手を離れ、新天地で一人やっていけるのかという不安がないわけではない。
しかも、気持ちが変わらなければ全てに決着が着いた後。
そんな白狼の気持ちを察したのか、匠海が頭を掻く。
「ジジイ、悪いな」
めんどくさい役を押し付けたかもしれない、と匠海が謝る。
そんなことないさ、と白狼が笑う。
「もう、会うこともないのかな」
「たまには電話しろよ」
寂しいことを言うな、この馬鹿者がと軽く小突きながら白狼が言った。
「そうだな、たまには電話する」
そう言ってから、匠海はふと、何かを思いついたような顔をする。
「……?」
訝し気に様子を窺う白狼を前に、匠海が自分の首に手を回す。
首にかけたチェーンを外し、白狼の前に突き出す。
「これ、預かってもらえないか?」
匠海が白狼に渡そうとしたのは和美の葬儀以降ずっと身に着けていた、二人の指輪をチェーンに通したペンダント。
そんなものを、と白狼は驚きを隠せなかった。
匠海にとっては処分せずに残した唯一の形見だろう。
アメリカ行きが決まってから、彼は今後の活動に必要なものだけをまとめ全て処分している。
それは和美の遺品も含めた全てで、全てが終わっても匠海はもう日本に戻ってくるつもりはないのだと、いや、現世に留まるつもりはないのだと白狼は思い知らされたものだった。
その指輪を、匠海は自分に託そうとしている。
彼にとってそれがとても大切なものであるということは想像に難くない。
そんなものを託されても嬉しくも何もない。
ふざけるな、と言おうとしてから顔をしかめ、言葉を紡ぎ直す。
「匠海、お前」
「ジジイにしか預けられないから」
だから頼む、と匠海は続けた。
それを、白狼は、
「いや、預かれない」
そう、きっぱりと断った。
「んな、形見分けみたいなことするな。それはお前が持っていてこそ、だ」
「だが……」
「ええいまどろっこしい、儂は受け取らんぞ」
両手を上げ、白狼が「絶対に受け取らない」と宣言する。
「匠海」
両手を上げたまま、白狼は諭すように口を開く。
「
「ジジイ……」
そこまで言われて、匠海も諦めたのか。
腕を下ろし、それから再びチェーンを首にかける。
「やっぱり今のお前にはそれは必要だよ」
そうだな、と匠海が頷く。
それから腕時計を見て「そろそろだ」と呟く。
「もう行かないと」
「ああ、向こうでもちゃんとやれよ」
ああ、と頷き匠海が踵を返す。
「またな、匠海」
匠海の後ろ姿に白狼が声をかける。
匠海が片手を挙げ、ひらひらと振った。
「
匠海の姿が搭乗ゲートの向こうに消える。
「『じゃあな』、か……」
少し寂しそうに呟き、白狼は搭乗ゲートを一瞥、それから踵を返す。
空港を出て空を見上げる。
上空を、匠海が乗っているものだろうか、ジェット機が飛んでいく。
「匠海……」
そう呟いてから、白狼はパン、と両手を合わせた。
「さて、儂も久々に本気を出すか」
意味ありげに呟き、白狼は駐車場に向かって歩き出した。
◆◇◆ ◆◇◆
匠海がアメリカへ渡ってから約一年。
世界樹での勤務は時には厄介なハッカーに侵入されることもあるが匠海の実力はそれすら上回るものとして周りに認められていった。
それはそうだろう、周りの先輩と違い、匠海は唯一世界樹の最深部のコンソールにフラグを残した人間。
白狼はまだまだだと言っていたがそれはあくまでも彼の目から見た匠海であって、周りの評価はそうではなかった。
スポーツハッキングチーム「キャメロット」、その最強の魔術師「アーサー」が来たと世界樹の監視室は沸いたものだ。
匠海としてはむず痒いものがあったがそれでも監視室の面々に受け入れられ、それなりに慌ただしい日々を送っている。
今日も仕事を終え、アパートメントの近くのコンビニで夕飯を買い出し、家に帰る。
指紋認証で玄関のロックを解除し、ドアを開けようとして。
「……?」
違和感を覚える。
しかしこの部屋は玄関は指紋認証、他の窓も外出時は電子ロックがかかるようになっている上にそもそも某アメコミヒーローでもない限り登ってこれないような階層にある。
侵入者など入れるはずもないのだが、中に誰かいるような気がする。
やばい、銃なんて持ってないぞどうする、と思いながら匠海はドアノブに手をかけた。
誰もいないことを祈りつつ、恐る恐るドアを開ける。
そろり、とドアの隙間から身を滑り込ませ、照明を点ける。
その瞬間、匠海の視界にとある情景が飛び込んできた。
厳密には、
一瞬、匠海は目を疑った。
幻覚を見ているのではないか、と現実逃避してしまう。
どうして。
「どうしてここにいるんだよジジイ!!!!」
どうしても目の前のことが信じられずに匠海が絶叫する。
おう、とソファに腰かけた侵入者――白狼が片手を挙げる。
「久しぶりだな、匠海」
時々通話はしていたものの1年ぶりにリアルで会う白狼は全く変わっていなかった。
相変わらずの派手なアロハシャツ姿に「ほんと変わらないな」と匠海は思った。
「一体どういうことだよ」
「あぁ、やっぱりお前が心配でな。一年かかったが追いかけさせてもらったよ」
「……」
白狼の言い分に匠海が額に手を当てる。
「ストーカーかよ」
少々呆れ果てた匠海の声。
いいだろ気にするなと白狼は豪快に笑う。
「まぁ、和美さんに頼まれてるからな、『助けてやってくれ』と」
「だが追いかけてくるなんて」
そう言ってから、匠海はふとあることに気が付いた。
「『一年かかった』?」
「そこに反応するのかよ」
それだけ答えてから白狼は嬉しそうに匠海を見る。
「まだ生きてたな」
「……ああ」
少々苦々しく匠海が頷く。
「まだ生きている」ということはあの事件の犯人にはまだ辿り着けていないということになる。
それは白狼にとっては少々ほっとする事ではあったが匠海には辛い事実であるだろう。
そこまで思ってから、白狼はふと思い出したことを口にする。
「和美さんの命日には?」
「ああ、一度帰国した」
やはりな、と一言だけ呟き、それから白狼は、
「だったら儂に会いに来てもいいだろうが!」
そう、声を上げた。
その白狼の抗議に臆することなく匠海は別に、と答える。
「ジジイには特に用はなかったからな」
ヒドイ、と白狼が呟く。
それでも、白狼は匠海が変わらずにいるということは安心できた。
逆に言えばまだ和美の幻影に囚われているのだと。
それに複雑な感情を抱きつつも白狼は仕事はどうだ、と尋ねた。
「まあ、それなりにな」
それよりどうすんだよ夕飯自分の分しか買ってないぞと文句を言いつつ匠海はテーブルにコンビニの袋を置き白狼を見る。
「ああ、気にすんな」
儂はお前が帰ってくる前に食ってきたからそれお前食っていいぞ腹減ってるだろ、と続ける。
それじゃ遠慮なく、と匠海がコンビニの袋からサンドイッチを取り出す。
サンドイッチを頬張る匠海を眺めながら、白狼は小さくため息を吐いた。
「いつもそれか? ゴミ箱の中身もコンビニ飯ばかりだし」
「別にいいだろ」
忙しいんだよと言いながら匠海がサンドイッチを飲み込み、コーヒーで流し込む。
不摂生だなあ、コーヒーの量も増えている気がするし心配だなあと匠海を見ながら思う白狼。
匠海もそれに気づいたのか、ばつが悪そうに白狼を見る。
「別に無理はしてないぞ。ジジイが心配するほどじゃない」
「それならいいが」
そこで、会話がいったん止まる。
暫く沈黙が続き、それに耐えられなくなった匠海が先に口を開いた。
「ところでジジイ」
「なんだ?」
「どれくらい滞在する気なんだ?」
ふと、気になった質問。
匠海の問いかけに、白狼は「あー……」と頭を掻いた。
「死ぬまで、かな」
「……は?」
白狼の言葉に匠海が素っ頓狂な声を上げる。
「死ぬまで……って、それ、まさか、永住……?」
「ああ、そのつもりだが?」
あっけらかんという白狼に匠海がちょっと待てと声を上げる。
「いや意味分からん。永住って、そう簡単にできるはずが」
匠海もちゃんと調べたから分かっている。
アメリカに永住するには
それには匠海のように就労ビザを取得したうえでアメリカの企業にスポンサーになってもらうものの他にはアメリカ国籍の人間と結婚するか
スポンサーを付けるのも時間のかかる方法だし白狼はそもそも就労ビザを取得できる条件を満たしていないはず、DVプログラムに至っては運任せ、そう考えると。
「まさかジジイ再婚したのか?!」
「はぁ?!」
匠海の「嘘だろ?!」と言わんばかりの言葉に白狼がんなわけあるかと反論する。
「儂の嫁は奈緒美ちゃんだけだ! 再婚など、せんわ!」
「じゃーどうやってグリーンカード取得したんだよ!」
全く訳が分からない。
だがそう考えるとDVプログラムに当選したとしか考えられないがそんな簡単に当選するとは到底思えない。
しかし、白狼は。
「勿論、DVプログラムに応募して当選したが?」
そう、あっけらかんとして答えた。
「……はぁ?」
今度は匠海が声を上げる番である。
そんな運任せのものに一発当選するなど考えられない。
――いや。
たった一つだけ、白狼が確実に当選する方法があった。
匠海の拳が固く握られる。
「ジジイ……」
そう呼びかける匠海の声が震えている。
「てめぇ、
「あ、バレた」
まさかそんな不正が行われていたとは、いや、このジジイならやりかねない、と匠海は自分に言い聞かせる。
「なんでそこまで」
「えー、ほら、ユグ鯖のお膝元だし今後の活動拠点をアメリカに移すのも悪くないかなと思ってな」
そう言い、白狼は立ち上がった。
「じゃ、匠海の生存確認もしたし儂も家に帰る。安心しろ、ちゃんとアパートメント契約してる」
「……はぁ」
ひらひらと片手を振り、玄関に向かう白狼の背を視線だけで追い、匠海は「なんだったんだ……」と考えた。
まさか白狼までもが自分を追ってアメリカに来るとは。
そこまで慕われるようなことをしたっけ、などと思いつつ匠海は玄関のドアが閉まるのを確認した。
「ジジイ……」
白狼の言葉は嘘だ、と勘が告げる。
その本心は。
「……ありがとう、ジジイ」
匠海が呟く。
たとえ自分がその厚意を受け入れられなかったとしても、白狼のその行動は嬉しかった。
慣れない土地での生活、確かに不安は大きい。
そこに唯一の家族が来てくれたことはとても心強かった。
「……ジジイ、あんたは最高の親父だよ」
ふと、匠海の口からそんな言葉が漏れた。
夜の街を歩き、白狼が自分のアパートメントに向かう。
久しぶりにリアルで会った匠海との会話を思い出し、くつくつと笑う。
帰ってきた時の匠海の驚きようはしっかりと録画している。
何かあった時の話のネタにしようと目論みつつ白狼は足を進める。
匠海が元気そうなのは確認できた。
強がっているだけだろうし心の傷は癒えていないだろうがそれでも日常生活が送れているのならそれでいいだろう。
世界樹での仕事ぶりも実は匠海の数か月後に同じく世界樹行きとなった
ガウェインも匠海が心配でスポーツハッキングのランカーという立場を捨て、世界樹をハッキング、司法取引をしたという。
儂も世界樹をハッキングした方が手っ取り早く移住できたのかなあ、だが流石に世界樹の運営をスポンサーにしても難しかったかもしれないからなあなどと思う。
DVプログラムの抽選を行うK.C.センターをハッキングしたとはいえ、それ以外は正規の手順だったため1年以上という時間を要したがこうやって今、白狼は匠海と同じ大地に立っている。
ふと立ち止まり、白狼は空を見上げた。
「……頑張ってるな、匠海」
今の彼を突き動かしているのはまだ犯人に対する憎しみだけだろうか。
できれば、その感情に変化が起こっていればいいが、と願ってしまう。
それでもその感情を抱えたままよく頑張っている、純粋にそう思う。
「……匠海……」
空を見上げたまま、呟く。
「そんな状態でもな、儂にとってお前は最高の息子なんだよ」
その声が、街の喧騒に呑まれて消えていった。