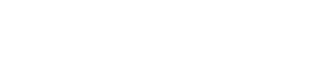ただ想い出だけをその胸に宿し
――貴方を、信じてる。
その言葉にハッと目を見開き、身体を起こす。
夢か、と思うものの最後に聞いた彼女の声は声から忘れていくという定説に関係なくいまだに鮮明に思い出せる。
「……和美、」
絞り出すように匠海が呟く。
逢いたい、声を聴きたい、抱きしめたい。
でもそれは叶わぬ夢。
叶わないと分かっているが、望んでしまう。
カレンダー付きの時計が「一番迎えたくない日」を刻んでいる。
ベッドから降りてカーテンを開け、匠海は差し込む朝日に目を細めた。
「……もう何年だ?」
行きつけのバーのカウンター席。
隣のスツールに腰掛けたガウェインがグラスに入ったウィスキーを回しながら呟く。
「4年、だな」
匠海も同じようにグラスに入ったジントニックを飲みながら呟く。
「墓参り、行ったのか?」
「ああ、いつも行ってるから」
そっか、とガウェインが言いながらウィスキーを一口飲み、それから改めて口を開く。
「命日くらい思い出話に花を咲かせてもいいだろ。
唐突に振られた話題に、匠海が困惑したようにガウェインを見る。
「いきなり何を」
「いや、なんか急に懐かしくなってな。お前とマーリンがえっちしたのが発覚して半年後の事故だろ、お前らどうだったんだよ」
「ぶっ!」
ガウェインの発言に匠海が飲みかけのジントニックを吹き出す。
「お、お前、何を!」
「やっぱ気持ちいいものなのか?
こいつ、分かって言ってやがる、と匠海は心の中で拳を握りしめた。
あの時確かに発覚するきっかけの発言をしたのは自分だ。
だからといってそれを、よりによって命日に持ち出すのはいただけない。
ほんの少しだけイラッとして、匠海は「じゃあお望み通り話してやろうじゃないか」と心を決めた。
ガウェインは一見プレイボーイに見えるが実は割とシャイである。少し刺激の強い話をすればすぐに落ちるだろう。
ああ、と匠海が頷いた。
「あれは経験した人間じゃないと分からない気持ちよさがあるぞ」
「マジか」
やや食い気味のガウェイン。
「や、やっぱ自分でやるのとは違うのか?」
ガウェインの問いかけに再びああ、と頷く匠海。
「柔らかいんだよ、和美の身体。ふわふわでもちもちで、本当に
「お……おぉ……」
そう言い、ごくりと唾を飲むガウェインに匠海は内心ニヤリとする。
この調子でいけばもう少し刺激の強い話をすればガウェインは赤くなって逃げ出すに違いない。
そう思いつつも、匠海はもう4年も前になる和美との情事を思い出した。
自分の腕の中で震え、求めてくる和美の汗ばんだ肌の感触や吐息がありありと思い出され、思わず顔をしかめる。
あの時の昂りを、もう一度味わいたい、そう思ってしまう。
「初めての時は俺だって未経験だったんだ。それなのにあの時のあいつは……」
ほんと凄かった、と匠海がポツリとこぼすとガウェインの顔が赤く染まる。
「凄かった、って、ど、どんな感じなんだ? マーリンって、ベッドの上では性格変わる感じ?」
それはどうだろう、と匠海は考えた。
普段の強気な雰囲気はどこにもなく、ただただ甘く匠海を呼んだ和美は確かに「性格が変わる」と言えたかもしれない。
そうだな、と匠海が頷いた。
「普段の強気なんて、だったな。とにかく可愛かった」
「ご馳走様でーす」
それは惚気なんだよ、とガウェインにツッコまれて匠海は「なんだよ」とふくれる。
「お前が振ったんだろ、なんでそこでそうなる」
「いや、思ってた以上に甘くてな……砂糖吐きそう」
そう言いながらガウェインがウィスキーを呷る。
「……辛いな」
空になったグラスを握ったまま、ガウェインがふと呟いた。
一瞬、面食らったものの匠海もすぐに真顔になりああ、と頷く。
「あんな時間がずっと続くと思ってた」
「そっか……」
悲痛な面持ちでガウェインが呟き、マスターにおかわりをオーダーする。
マスターがグラスに氷を入れ、新たにウィスキーを注いでガウェインの前に置く。
「おかわりはいかがですか?」
にこやかなマスターの問いかけに、匠海も自分のグラスが空になっていることに気づいた。
「ああ、頼む。お任せでもいいか?」
匠海がそう言うと、マスターが笑顔を崩さず「かしこまりました」とグラスを手に取る。
氷の後に注がれたウォッカとグレープフルーツジュース。
マスターの手つきを見ていた匠海の顔色が変わる。
「マスター、それ……」
グラスの中身を軽く
「
「なん、で……」
どうして、と言わんばかりの匠海の顔。
怪訝そうな顔でガウェインが様子を見ている。
「先程の会話で『命日だ』と小耳に挟みましたので。
「……」
最初に受けた衝撃を振り払い、匠海がそっとグラスを手に取る。
「『守りたい』、か……」
「ん?」
匠海の言葉にガウェインが首を傾げる。
「ブルドッグのカクテル言葉だ。あいつは、俺と飲む時は必ずこれを飲んでいた」
「
ガウェインはなんとなく察してしまった。
和美は誰かと差しで飲む時は相手に合わせてカクテルを変えていた。
ガウェインには理解できていなかったが、それが和美にとっての相手へのメッセージだったのだろう。
そして、和美は無言で匠海を「守りたい」と言っていたのだと。
「カクテル言葉を知ったのはあいつが死んでからだ。もし、知っていれば、あんなことはさせなかったのに」
和美は言葉通り匠海を守って死んだ。
それは、彼にとって深い傷になったはずだ。
いや、現に彼はまだPTSDを克服できていない。
妖精の出自を知り、彼女を守ると誓ってからある程度は克服していたが完全に乗り越えるのは無理なんだろうな、とガウェインは思っている。
ぽん、とガウェインが匠海の肩を叩く。
「いつまでも自分を責めるな。マーリンはそんなこと望んでないだろ」
そう言いながらガウェインは匠海の左肩で暇そうにジュースを飲む妖精を見た。
「すまんな妖精、今日はアーサー貸切だ」
『いいよー。その方が
ずずー、とストローでジュースを飲み干した妖精がウィンドウを開き追加のジュースを展開する。
『で、さっきの話の続き、オリジナルってそんなに感度よかったの?』
「ぶっ!」
妖精の言葉に匠海が再度吹き出す。
「お、おま……なんてことを」
『えー、タクミから見たオリジナルの話は貴重じゃない。わたしのライブラリにもないんだからさー』
ようせえぇぇぇぇ、と、匠海が恨みがましそうに唸る。
ひとしきり唸ってから、
「ああ、もう最高だった。
過去最高に投げやりな口調で、匠海が言い捨てた。
「ぶっ!」
投げやりな匠海の言葉に今度はガウェインが吹き出す。
「ちょ、アーサー!」
まさかそんな言葉が飛び出してくるとは思っていなかったのだろう、ガウェインが何故か抗議する。
「お前はマーリンに対する敬意ってもんがないのか!」
「敬意もなんでもあるぞ。今でも愛してるのは事実だ」
さらりと匠海の口から溢れる「愛してる」の単語。
一途だな、とガウェインは素直にそう思った。
――マーリン、あんたやっぱり愛されてるよ。
そうガウェインが思っていたら。
『でもさー、ライブラリ見る限りタクミってオリジナルが生きてるうちに「愛してる」なんて一言も言わなかったよね』
妖精がとんでもない爆弾を投下した。
「アーサーーーー!!!!」
お前、なんでそんな大事なことを! とガウェインが声を上げる。
ああ、と匠海が小さく頷いた。
その悲痛そうな面持ちにガウェインも真顔に戻る。
「お前……」
「恥ずかしかったんだ、『愛してる』って言うのが。いつかは言えると思ってたが、結局最期まで……」
それが和美に対する最大の後悔だ、と匠海はガウェインに打ち明けた。
「アーサー……」
聞いてはいけないことを聞いてしまった、とガウェインがふと思う。
そして、
「今日は俺の奢りだ、飲んで思い出話して、今夜はとことん付き合うぜ」
そう、努めて明るく宣言する。
「明日、俺、早番なんだが」
ガウェインの言葉に不服を唱えながらも匠海がふと笑う。
「ありがとう、ガウェイン」
「気にすんな、俺とお前の仲だろ」
そう言って、ガウェインは匠海の肩をポンと叩いた。