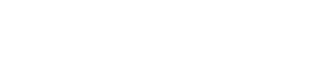理想郷は誰の夢を見るか
空はどんよりと曇り、今にも降り出しそうな様相を呈していた。
音もなくレールを滑る列車はカーブに差し掛かり、その先に聳える巨大な建造物の立ち並ぶ都市を少しずつ乗客に見せてくる。
「ねえ、アルカディアってどんなところだと思う?」
ボックス席の向かいに座る彼女が努めて明るく僕にそう訊ねてくる。
「さあ、何不自由なく暮らせる都市という噂しか聞かないからなんとも」
曇り空に自分の心を投影しながら僕は素直に答える。
移住を許可されれば何一つ不自由なく生涯を過ごせると噂される理想都市、「アルカディア」。
飢えることも凍えることもなく、ただ満たされた一生を過ごせるのだと多くの人間がこの都市を目指した。
度重なる天変地異とそれによって荒んだ人間が引き起こした戦争により多くの人間が疲弊し、理想都市と呼ばれるこの地を目指した。
人間が勝手に作り出したルールや試練で多くの人間がふるい落とされ、アルカディアにつながる唯一の手段であるこの列車に乗ることができるのはほんの一握り。
チケットを入手し、列車に乗り込んでしまえばあとは最後の試練、アルカディアが課す入場審査を通過するだけ。
しかし審査に落ちて戻ってきた人間は誰一人おらず、また、移住を許された人間もその快適さからか誰一人アルカディアから出てこないためどのような場所かは誰も知らない。
ただ、時折ラジオに流れるアルカディアのプロモーションでこの都市が「理想郷」であることは推測できた。
目の前の彼女が窓の外を、そして列車が向かう先にある都市を見る。
「ねえ、君はアルカディアの移住が許されたら何がしたい?」
「『何がしたい』って……」
彼女の問いかけに、僕は言葉に詰まった。
何がしたいのだろう。
僕が生まれた時にはすでに戦争が始まって久しく、僕はその日を生きるだけで精いっぱいだった。
何がしたいか、と聞かれても「生きたい」以外の答えが見つからない。
娯楽というものは存在するらしいがその「娯楽」とはどういうものか想像すらできない。
そんなことを考えていると彼女が僕に手を伸ばし、手を握り締めた。
「きっと、何でもできるよ。やりたいこと、見つかるといいね」
不自由のない理想郷だから。きっと「娯楽」もそこにある。
うん、と頷いて僕も近づきつつある都市を見た。
と、不意に音もなく列車が停止する。
直後、全ての窓が開け放たれ、外から生ぬるい風が吹き込んでくる。
嫌な風だ、と僕は思った。
身を乗り出して外を見ると都市から無数の何かが飛来するのが見える。
無数の何かはあっと言う間に列車に到達し、窓から車内に入り込んできた。
何かは乗客一人一人の目の前で停止する。
それは正面にアイボールのある機械だった。
車内のスピーカーが一瞬ノイズを上げ、そして乗客全員に告げる。
『ただ今より移住のための審査を行います』
目の前の機械のアイボールが光り、それぞれが乗客一人一人を担当するかのようにスキャンを始める。
恐らくは個人に割り当てられた
時間にしてほんの数分もかかったかどうか、それでもとても長い時間が経過したような錯覚を覚えた時、目の前の機械のアイボールが緑に光る。
『おめでとうございます。貴方は住人として認められました』
その音声に、僕はほっと息を吐いた。
最後の試練はクリアした。アルカディアは僕を受け入れた。
そう思って向かいの席に座る彼女を見ると、彼女は怯えた目でこちらを見ていた。
『貴方はアルカディアには不要の存在です』
彼女の目の前の機械からそんな音声が聞こえる。
『不要な存在は抹消します』
機械のアイボールが不気味に光る。
咄嗟に僕は彼女の手を引いた。
アイボールから放たれた光線が座席の背もたれを灼く。
そこここから叫び声が上がり、車内は騒然としていた。
彼女の手を引き、転がるように通路に出る。
走って、後ろの車両へ向かおうとする。
「あっ」
彼女が足をもつれさせ、転倒しそうになるのを支えて回避、後ろの車両へ向かう。
「……っ!」
目の前の光景はどう見ても酷いものだった。
機械によって「不要」と判断された人間の成れの果てがそこここに転がっている。
そのどれもが首のない死体で、よく見ると機械が切り落とした首をアームで抱えて窓から外に運び出している。
それを横目で見ながら僕は彼女と一緒に最後尾の車両に逃げ込んだ。
そこでも今までの車両と変わらないことが行われていたが、ここは最後尾、逃げるならここしかない。
彼女のすぐ横を光線が奔り、座席を灼く。
それには構わず、僕は彼女の手を引いた。
車両のさらに最後尾、後部には外につながるデッキがある。
デッキには非常用のはしごがあり、そこからこの列車から脱出することができるはず。
手を差し出し、僕は彼女を列車の外へと導いた。
どうやら僕の「受け入れる」という態勢は解除されていないようで、僕がいることで彼女を狙う機械は光線を放てない。
行ける、と僕は彼女が線路に降りるのを確認してはしごを滑り降りた。
線路の上で待っていた彼女の手を引き、再び走り出す。
「どうするの?」
不安そうな顔で、彼女は僕に問う。
「分からないよ! だけど、アルカディアが理想郷なんて、真っ赤な嘘だ!」
移住希望者の大半を不要なものとして殺しておいて、認められた者が幸せになるとはどうしても思えない。
僕は認められたが、アルカディアに移住するのはできない、と思ってしまった。
逃げるしかない。あの機械が彼女を諦めるまで。
時折飛んでくる光線を避けながらも、僕は彼女と一緒に走り続けた。
線路の周りに見える草原はところどころに捨てられた首が転がり、花が咲いているかのような風景に変わりつつある。
暫く走り続けると、追跡を諦めたのか機械が都市へと舞い戻っていく。
後ろの方に取り残された列車も、認められた人と死体を乗せたまま動き出し、都市に入っていく。
「……いいの?」
列車が都市の中に消えていく様子を見送った彼女が口を開く。
「私のことなんて放っておいてもよかったのに」
君は認められたじゃない、と彼女が言うが、僕はもうアルカディアなんてものはどうでもよかった。
確かに、理想郷なら住人の厳選くらいするだろう。
不要だと思った人間を排除するのもこの殺伐とした世界なら当たり前だろう。
だけど。それでも。
僕はアルカディアより彼女を選んでしまった。
僕よりも、誰よりもアルカディアを期待し、移住した後の未来を夢見ていた彼女が許されないのなら、僕一人で移住してもきっと何も面白くない。
ただ満たされただけの、何も存在しない空っぽの人生なんてほしくない。
それなら、僕は彼女と生き延びたいと思った。
どれだけの苦難が待っているかも分からない。
アルカディアは本当に僕が漠然と望んでいた理想郷だったかもしれない。
だけど、僕は彼女と共にありたいと思った。
僕の旅路を、彼女という不確定要素で彩りたい。
「僕は、君と一緒に旅をしたいと思った」
僕がそう言うと、彼女は意外そうな顔をする。
「……それって、私のことが好きになっちゃったとか?」
それは分からない。
生きるので精いっぱいのこの世界で、恋愛感情なんてものが実在するのかどうかなんてわからないしそんなものはどうでもいい。
でも、僕は彼女といっしょに「いきたい」と思った。
それを彼女に伝える。彼女がはにかんだように笑う。
「……じゃ、いこっか」
彼女が僕の手を握る。僕も彼女の手を握り返す。
列車が走り去り、回りには生首の花が咲くこの狂った地から。
僕たちの旅は始まる。
たとえどんなに苦しくても。
たとえどんなに辛くても。
僕と彼女の二人ならきっと歩んでいける。
僕たちは歩き出した。
僕たちだけの