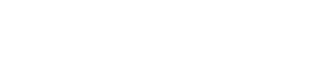魂の所在-The third soul-
第1章 目覚め
カーテンから差し込む朝日に、「僕」は目を開けた。
病室の天井は相変わらず白く、点滴のパックをぶら下げる金具はぶらぶらと揺れている。そこにぶら下がっていたパックは数日前から外され、身動きは自由にできた。
無理もない、「僕」は今日退院する。交通事故に遭い、入院を余儀なくされていたが幸い怪我らしい怪我もなく、暇を持て余していたくらいだ。ただ、気になったのは殆ど怪我がなかったのに入院期間が長引いた理由だ。
医師は「頭を強く打ち、脳に異常がある可能性がある」と説明したが意識はしっかりあり、思うように動けないということもなかった。とはいえ、やはり事故の影響だろうか、事故前後の記憶が全くない。それで医師も検査を繰り返したのだろう。
しかし今回の事故には不可解な点が多い。トラックに衝突したという話だったがそれなら大怪我をしていても不思議ではない。ほぼ無傷、ということが奇跡に近い。だからだろう、この病院――とある医科大学の附属病院である――で様々な検査を受ける羽目になったのは。事故前後の記憶がなかったのもその検査の一因となっている。
カーテンを開け、ぼんやりと外を見る。季節は春で、河川敷の桜が満開になっている。
結局、大学生活最後の春休みを丸ごと入院に費やした挙句、退院してすぐに新社会人としての生活を送ることになるのか、それなのに何度も休みを取って通院するという、新入社員としては非常に迷惑なことになってしまった、と風に舞う花びらを見ながら思う。
見舞いに来てくれた友人と花見もいいな、だが今から企画したのではもう遅いか。そんなことを考えながら朝食を待つ。そのうち同室の入院患者も起床し、廊下も徐々に騒がしくなる。
看護師が検温に来て、「今日退院ですね」と声をかけてくる。退院と言っても、まだ月に数回の検査が残っているためこの病院にはちょくちょく顔を出すことになるだろう。そう告げると「それならシュークリームでも持ってナースセンターまで遊びに来てくださいよ」と冗談が返ってくる。確かこの病院は医師、看護師等に差し入れを持っていくことは禁止だったはずだが、と思わずまじめに考えてしまうが自分の回復を喜んでいるのだろう、と解釈する。
そんな話をしているうちに朝食が配膳され、看護師が病室を出る。
朝食を食べ終え、「僕」は荷物をまとめた。退院手続きを行い、支払いの請求書を受け取り、数人の看護師が見送る中「僕」は退院した。
「僕」の退院を知ったタカユキがアパートに押しかけてきたのは帰宅した直後だった。相変わらず情報が早い奴だ、と思う。大学に入学してからずっと付き合いのある彼は「僕」の入院中もちょくちょく差し入れを持って見舞いに来てくれた。他の友人も何度か来たが、タカユキほど頻繁に来た友人はいないだろう。
「相変わらず
タカユキの発言は相変わらず唐突で、意図がつかめない。「僕」が戸惑っていたのをすぐに察したのだろう、次の言葉で説明をしてくる。
「お前の退院を祝ってな、飲み会をやろうということになったんだ。お前が来ないと話にならないから顔出せ。酒は呑んでも呑まれるな、だ」
最後の一言が余計な気がするが、「僕」の退院を喜んでくれていることはすぐに分かった。元々飲みかわすことは嫌いではなく、友人たちが喜んでくれているのなら参加すべきだろう。
そう思い、「僕」は頷いて財布を手に取った。
よく行く居酒屋に、「僕」やタカユキ、それから数人の友人が集まっていた。
友人が「僕」の姿を見て「退院おめでとう」や「よく生きてたな」と口々に言い、今日の主役は「僕」だと言わんばかりに上座に座らせようとする。
全員がとりあえず
「シシャモのから揚げ」を「僕」が注文したときだった。
タカユキの顔色が変わる。
「あれ、お前シシャモなんて食うのか?」
タカユキの言葉に、メニューを閉じようとした「僕」の手が止まる。他の友人も、意外そうな顔をして「僕」を見ていた。
「お前、いつもレバー串頼むだろ、好物だって言ってただろうに」
その言葉に「えっ、」と声を上げる「僕」。レバー串なんて、全く好物ではない。むしろ嫌いな部類に入るだろう。
「僕」のその反応に、タカユキがまあ、と呟いた。事故のショックで好みが変わることもあるのだろう、と解釈したのだろうか。
しかし、自分がレバー串が好みだとは信じられない。昔からシシャモが好きだったはず。だが、記憶の糸を手繰ると確かに「僕」はレバー串を好んで食べていた、ということに気付く。
嘘だろう、レバーのどこがおいしいのだ、と腑に落ちなかったがそんなことを考えていると脳内にイメージが展開される。
レバーにはビタミンや鉄分、葉酸などが多く含まれている。特に豚レバーはタンパク質や鉄分が多く、貧血の人間は積極的に摂るべきだ――。
まただ、と「僕」は思った。
「僕」は時々目や耳にしたものの知識がウィキペディアの該当ページを閲覧しているかのように脳内にイメージが広がる。
そのおかげで大学の成績もトップで、身寄りのない「僕」は返済の必要のない給付型の奨学金の支給を受けることもできたが自分でも気持ち悪い、と思うことがある。
まさかレバーでこれを見ることになるとは、と思っている間に生中が届き、乾杯する。
「そういえば、お前、後遺症はないのか?」
不意に、友人の一人がそう尋ねてくる。タカユキは看護師から詳しい説明を聞いていたらしく「僕」の入院中にそのあたりの話をしてくることはなかったが、気になっていたのだろう。「僕」が後遺症も何もない、と答えると友人が不思議だよな、と呟く。
「トラックにはねられた割には無傷とか奇跡がどれだけ重なったら起こるんだよ。いや、お前が死んでくれたらって思ったわけじゃないが、本当にトラックにはねられたのか、なんてな」
そうだ。確かにトラックにはねられてほぼ無傷というのは奇跡だろう。といっても事故前後の記憶は全くなく、トラックにはねられたというのも医師にそう言われたからであって「僕」は全く覚えていない。
そこまで考えてから、「僕」はあれっと思った。
事故前後の記憶――いや、事故の数日前の記憶が全くない。「僕」が覚えているのは事故の数日前、とある持病の検査で病院――これも入院していたところと同じ医科大学の附属病院だ――に行ったところが最後だった。そこから事故まで、自分は一体何をしていたのだろうか。確かに事故前後の記憶が抜け落ちるということはあるらしいがそれでも数日の記憶がないのは何かがおかしい。
シシャモのから揚げをかじりながら、「僕」はなんとなく噛み合わない自分の記憶について考え込んでいた。