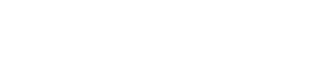魂の所在-The third soul-
これまでのあらすじ(クリックタップで展開)
事故での入院の後、退院した「僕」は退院祝いの飲み会で好みの食べ物について指摘を受ける。
その後の持病の通院で「アカネ」と名乗る医師に出会った「僕」は持病を別の視点からアプローチしたいと言われ、検査を受けるも何かを知っている様子に問い詰めると彼女は病院内に逃げ込んでしまう。
夜になって病院に忍び込んだ「僕」とタカユキはそこで「僕」そっくりの人間を見る。
そこに現れた「主任」の話によると、「僕」は「死の克服」のために記憶を別の人間に転写するというプロジェクトの被検体らしい。
記憶の転写が完全ではないという事実に主任は「僕」を捕え、解剖しようとする。
その手から逃れるため、「僕」とタカユキはアカネの手を借りて病院を脱出する。
第4章 魂の所在
どれくらい走ったのだろうか。夢中になってアカネと走っていたが、彼女が立ち止まったことで「僕」も足を止める。追っ手もなく、少しほっとして周りを見たら。
そこは墓地だった。数多くの墓標が立ち並び、深夜の闇が墓地のところどころに設置されている街灯の明かりで切り裂かれている。
その闇をさらにタカユキとアカネが持つペンライトの光が切り裂き、墓標を照らし出す。
「ここは……」
タカユキがぐるりと周りを見て呟く。
「ここよ」
一つの墓標の前に歩み寄り、アカネが手招きする。「僕」も歩み寄り、アカネのペンライトを借りて墓碑銘を見た。
暫くの沈黙。
ごくり、と唾を飲み込む音が響いた気がした。
「嘘……だろ……?」
それは「僕」が言いたかった台詞だった。
墓碑銘として刻まれていたのは、「僕」の名前だった。つまり、「僕」のオリジナルは。
「そうよ、貴方のオリジナルは貴方と交通事故で死んだ前の貴方が起動される前に事故で死んでいる。亡くなる直前に、主任に言ったそうよ。『僕の死が未来につながるなら喜んで被検体になる』と」
「そんなことがあってたまるか……」
弱々しく呟くタカユキ。そして、「僕」を見る。
「俺が見ていたのは何だったんだ。しかし、こいつ今年で新社会人の年齢だろ? それに俺とこいつは少なくとも大学の四年間を一緒に過ごしてきた。だったら研究者のオリジナルとやらと年齢が合わないしそもそも記憶だって」
そうだ。よくよく考えれば、「オリジナル」が研究者だというのに「僕」がそれより年下の大学生だった、ということもおかしい話だ。
いや、年齢に関しては実は「オリジナル」はずば抜けて頭がよく、飛び級で大学院を出て研究職になったということは十分考えられる。
しかし、「僕」には研究者だったころの記憶がない。
――いや、そもそも――。
「僕」は元々記憶の混乱が多い方だった。
あの「事故」前後の記憶がないように、数日の記憶が抜け落ちていることもよくある話で、小学校後半から高校を出るまでくらいはただ夢中に過ごしていて逆に何も覚えていない、という感じだった。
まさかそれも。
そう、アカネに問うと彼女は「その通りよ」と頷いた。
「飛び級で、本来なら小学校も卒業していないような年齢で大学院を卒業。十五歳の時点で理論的神経科学の第一人者と意見をぶつけ合えるほどの知識量と理論でとても有望視されていた。あの事故がなければ……」
そう言って、アカネは唇を噛む。
「本人の希望なのよ。『でもせめて、被検体としての僕は普通の人間として生きていきたい』って。その上で『皆の力で死の克服を実現して』と。だから研究者だったという部分の記憶は全て消した。記憶の抽出の研究の過程で消去することもできるようになっていたから」
そんな、とタカユキは唸った。
「信じられない……こいつがそんなことを言うなんて思えない」
その通りだ。「僕」は「死」を克服しようとなどは思っていない。「僕」のオリジナルはそう願ったのかもしれないが、それは間違いなのだ。
アカネが、数歩歩き、それからくるりと振り返る。
「どうして私がここに連れてきたか分かる? まあ、深い意味はないのだけど、貴方と『彼』は同一人物だ、という証明がしたかった。それだけよ」
その瞬間、タカユキが動いた。アカネの胸倉を掴み、視線だけで殺せそうな勢いで睨み付ける。
「何を今更! お前がこいつの検査をしなければこいつは何も知らずに生きることができた! こいつの人生を滅茶苦茶にしておいて、なにが『同一人物だ、という証明がしたかった』だ! ふざけるな!」
「……」
アカネは否定しなかった。肯定もしなかったが、その態度は肯定した、とも言えるだろう。彼女が自分の胸倉を掴むタカユキの目をまっすぐ受け止める。その自信に怯み、タカユキは手を放した。
「そもそも、『魂』ってどこに宿るのかしら」
唐突にそう告げられ、「僕」とタカユキは顔を見合わせた。別人の証明をしたいという割に、話の関連性がいまいち掴めない。それでも、「僕」は「僕」なりの答えを口にした。「魂」はその人間、いや、生物一つ一つに宿るのだ、と。
ところが、アカネはそれを否定した。
「……貴方の考えは漠然としすぎているわね。それじゃ質問を変えるわ。貴方の『魂』はどこに宿っていると思う?」
自分の「魂」の所在? そんなことは考えたことがなかった。どこに宿るか、それは思考を司る「脳」なのか、それとも肉体を維持する「心臓」か……そう迷いがちに答える。それに対しアカネはなるほど、と呟いた。
「確かに、『脳』なら脳死状態になると『魂』は消失したことになるし、『心臓』なら肉体が朽ちるときに『魂』は消失する。そんなところかしら」
彼女は一体何を言いたいのか。話が全く読めてこない。そんな「僕」にお構いなく、彼女は続ける。
「それじゃ、『生物』の定義は何になるのかしら」
それは、憶えている。生物の授業で学んだことだ。「生物」とはタンパク質からなり、酵素をはじめとした代謝の働き、そして核酸からなる遺伝子の働きを行う、その働きが「生命」となる、そう教わったものだ。ただしウィルスやリケッチアは特定条件が揃わないと増殖できないということから生物か、非生物かで長年議論されていたはずだ。
そこまで考えた瞬間、「僕」の脳内にイメージが広がった。
生命の模式図、DNAの二重らせん、分子図に――。
ダメだ、これ以上考えてはいけない。
「僕」が「僕」でなくなりそうな錯覚を覚える。
こんな知識を、「僕」が持っているわけがない。
飛び級で大学院を卒業? 理論的神経科学の第一人者と意見をぶつけ合った――?
そんなことがあるわけがない。「僕」にそんな過去なんてあるはずがない。
しかし、どうだ? 「僕」の記憶はこうもあやふやで、何一つ信じられない。
いや、今はそんなことを考えている場合ではない。アカネに問われたことに回答しなければ。
混乱する頭を落ち着け、最初に思い出した答えをを告げると、彼女からは「教科書やウィキペディアに記載されている完璧な解答ね」と返された。
「それじゃあ、最後の質問をするわ。貴方の肉体を構築している細胞の一つ一つ、それは『生命』?」
その瞬間、背筋を冷たいものが流れた気がした。細胞の一つ一つ。「僕」が答えた模範解答から当てはめると――それは個々の「生命」を持つということになる。つまり――。
「……『魂』は、細胞の数だけ存在する、というのか……?」
タカユキが「僕」の考えを代弁する。同じ遺伝子構造であっても、別の細胞であれば別の存在であると。
そして細胞は早いものであれば一か月、長くても二百日程度で入れ替わるという。
つまりそのサイクルで人間は「別人」に変わっていく、アカネはそう言いたいのか。
「そうよ。サイクルの都合を考えると全てが完全に入れ替わるのは大体七年と言われているわね。だから私も、貴方も既に何人かの『自分』と入れ替わっている」
「だが、それだとお前の『同一人物』という話はどうなる……?」
タカユキの問いに、アカネが小さく頷く。
そうだ。「入れ替わる」ことを「別人」と表現するのなら初めの「同一人物」という話と矛盾が生じる。
彼女は、「僕」を実験体にしているチームの一員である。「僕」が「以前の僕」と同一人物でなければ不都合があるのだろう。
だが、話を聞いていると矛盾だけでなく、迷いを感じた。
「本当に同一の存在」と見ていいのか、という迷いを。
そうだろう、「死」を克服することが目的で、別の肉体に「記憶」を転写することまではできた。だがその新しい肉体で以前の肉体と食い違う行動をとれば何もかもが破綻してしまう。それでは克服に遠く及ばない。
思わず、そう言うと彼女は「本当は機密事項だけど」と言いつつも口を開いた。
今、世界は「死」を克服する手段の一つとして別の個体に「記憶」を転写する研究を行っていた。
現時点では法があるため、人間をクローニングしてまっさらな肉体に記憶を転写することはできない。「記憶の転写」の研究、果ては「死の克服」を目指すようになり、人間のクローン作製を解禁しようとする動きは出てきているが未だに人権団体などの抵抗は大きい。
しかし近年、研究が実を結び人類は漸く生物、特に「人間」の記憶をコンピュータに抽出することに成功した。脳内データが膨大であるためそれなりの規模のデータセンタークラスのサーバは必要になるがそれでも人間の「記憶」は抽出し、保管することができるようになった。
保管ができるようになれば次は「転写」である。
記憶の抽出の研究過程で脳内の電気信号が全て解析され、任意の信号をぶつけることで記憶の消去も可能となっている。それを踏まえて、記憶の転写には検体として志願した人間が全ての記憶を消され、転写先として指定された。
その主な実験体が「僕」だというわけだ。
しかし、問題点もあった。前の「僕」から次の「僕」へ記憶を転写しても、全く同じ存在にはならなかった。それは「今」の「僕」にも当てはまることだ。どこかで人格や嗜好、思考などに齟齬が発生した。それでは、完璧に「死」を克服したことにはならない。主任は、何度も観測を続けていたがその謎は解明できなかった。
そこで彼女は一つの仮説を立てた。それが「生物」、「生命」を根本から見直した「『魂』は細胞の数だけ存在する」だった。とはいえその仮説にも矛盾が存在する。細胞一つ一つが一つの生命体なら、「人間」とは何なのか、と。
複合生命体、と突然彼女は新しい単語を口にした。
「複数の生命がつながり、助け合うことで一つの、全く別の生命体を構築する。それが多細胞生物の基本。でも、それだと『記憶』はどうなる、って話になるわね」
そうだ。記憶が置き去りになっている。結局、記憶とは何なのか。
「お前の言い分だと、『記憶』は細胞一つ一つに宿っているとしか思えんが」
そう、タカユキが言う。
細胞一つ一つの寿命は短い。
生物が何年、何十年と生きながらえるには細胞の入れ替わりが必要だろう。
しかし、細胞が入れ替わり、数年前と同じ細胞が無くなった状態――完全に入れ替わった状態でも、生物は記憶を失っていない。
それは細胞が入れ替わる際に、同時に記憶も継承されている、ということなのか。
実際のところ、一部の神経細胞などは入れ替わりが発生せず、損傷すればその部分は再生することがないと言われている。結果として、完全な入れ替わりはあり得ないのだが。
その「決して入れ替わらない」細胞によって「記憶」は保持されていると考えるべきだろう。
それとも。
――「決して入れ替わらない」細胞があるから、同一の存在と断言できるのか。
存在の同一性。
アカネが言いたいことはここにあるのだろうか。
本来ならゆっくり時間をかけて分裂した細胞に引き継がれる「記憶」。しかし転写という、急激に別個体に記憶を引き継ぐことで同一性が保たれなくなり、「前」と「後」の「僕」に齟齬が発生するのではないかと。
そうね、とアカネが頷いた。
「『テセウスの船』って知ってる? ある物体があって、その部品を全て交換した時その物体は「過去のそれ」と「現在のそれ」で同一か? という話」
「なんだそれ? 聞いたことねえな」
タカユキはそう言うが、「僕」は聞いたことがある。いや、友人と議論したことがある。
その時のメンバーにタカユキもいたと思っていたが、彼が「聞いたことがない」と言うのであれば、一体誰と議論したのか。
違う、これは「かつて」の「僕」の記憶だ。「かつて」の「僕」が、幼かったころの「僕」が自分よりはるかに年上の研究者仲間に臆することなく議論を戦わせたその記憶だ。
あの時「僕」はどう答えただろう。
議論した記憶はあるが、その結末を思い出せない。
それでも、今の「僕」は思った。
構成物質が変わっているから、「同一ではない」と。
それを告げると、アカネはふっと寂しそうな笑みをその顔に浮かべた。
「……やっぱり、貴方は『彼』とは違うのね」
あの時の「彼」の結論は「同一である」だったのよ、とアカネが続ける。
同じ「記憶」を引き継いでいるはずなのに、最終的な思考が違う。
いや、一部の記憶を消去したから思考が変わったのか。
何が相違に至ったかは分からない。
肉体が別だからか、環境が別だからか、記憶が完全に一致しないからか。
――いや、そんなことはどうでもいい。
今必要なのは。
今この瞬間に必要なのは。
「僕」はアカネの知る「彼」ではない、その事実だ。
いくら「記憶」が存在の同一性を告げたとしても。
その「記憶」も完全ではない、と。
現に、同じ議論を行った結果が変わったではないか。
そう考えると、「記憶」も流転するもの。
同じ存在を永劫につなぎ続けることは不可能なのだと。
クローンであれば多少は存在の同一性を保てるかもしれない。しかし、細胞一つ一つに宿る「魂」が違うのだから、結局別人になってしまうはずだ。つまり、この研究は完成しないのではないのか。それとも、何か策はあるのか。
「『魂』はまだあるという概念だけよ。でもその『魂』を観測することができればいずれは支配することができる」
もし、「魂」の同一性を保持する方法が発見されれば、肉体を変えても「同じ人間」として存在し続けることができるのではないか、と。
「そのためにこいつを犠牲にするのか? これ以上こいつを苦しめるのか?」
食って掛かるタカユキにアカネは小さくため息をついた。それは「仕方のないことよ」という意思表示なのだと「僕」は判断したが、彼女はため息の後に首を振った。
「……でも、『魂』の同一性が保持できたとして、本当に同じ人なのかしら」
分からない、とアカネが呟く。
「僕」もそれは同じだった。
仮に「魂」が同じであったとしても、本当に同じ存在だと言えるのか。
否、と「僕」の心が囁く。
そんなことはあり得ない、と。
しかし、その根拠が思いつかない。
考えろ、と「僕」は呟いた。
かつて大学を飛び級で卒業したという話が本当なら、この話題に「否」と断言できる根拠くらい見つけられるはずだ。
転写実験のせいで飛び飛びになっている記憶をつなぎ合わせる。
子供のころ、様々な学術誌や眉唾物のトンデモ理論など、様々な論文や本を読んでいたはずだ。
「記憶」や「魂」に関わる、何か――。
考え込んだ「僕」を見て、タカユキも何かを考え始めた。
「『魂』とか『記憶』とか分かんねーよ。ぶっちゃけ『テセウスの船』も聞いた感じじゃどっちとも言えるしさ……」
そう呟きながらタカユキが考え込んだ時の癖で手にしていたペンライトをペン回しの要領で器用に回す。
灯台の
「……器用ね」
タカユキの手元を見て、アカネが言う。
その言葉に我に返ったタカユキがペンライトを持ち直し、まあな、と頷く。
「考え事するとついついやっちまうからな……身体が憶えてんだよ」
それだ、と「僕」は思わず声を上げた。
突然の「僕」の声に、タカユキとアカネが「僕」を見る。
身体が憶えている、それなんだ、と「僕」は説明した。
脳が、
そして、気付く。これまで語り掛けてきた知識はオリジナルの「僕」の知識だったんだ。
身体が憶えている、という現象は一般的に繰り返して脳が憶えてそのように動く「手続き記憶」とされる。
だが、厳密には「手続き記憶」ではない「身体の記憶」が存在するという説もある。
味覚など各種感覚は感覚器官が瞬時に記憶し、脳に送られている。
本来ならその感覚の記憶はごく短時間で消えてしまうが、それが嗜好によって蓄積し、感覚器官自体が記憶してしまえば。
実際、「記憶転移」も存在すると言われているのである。臓器移植を行ったら、臓器移植元の嗜好が移植先に人間に発現するような。
それが「別の脳に記憶を移植した」が「同一の存在にならない」根拠ではないだろうか。
そう考えると、「僕」が「元の僕でない」という証明ができる。
以前、退院直後の飲み会で「僕」は「シシャモのから揚げ」を注文した。
それはタカユキから見れば「あり得ない」注文で、いつもなら「レバー串」を注文していた、という話があった。
今なら説明ができる。
「前」の「僕」はレバー串が好きだった。しかし記憶を転写された「今」の「僕」の本来はシシャモのから揚げが好きだった。
その嗜好が、「僕」を変化させた。
つまりそれは、「脳の記憶を消してもその人間を消すことはできない」証明になる。
同時に「脳の記憶を書き換えても元の人間の痕跡は残る」証明になる。
この肉体の記憶が解明されない限り、いや、解明され書き換えることができたとしても。
それこそ本当に「テセウスの船」の問題になる。
完全に同一のものになったとしても、その先はただの延長線になるのかすら分からない。
だから無駄なのだと。
記憶を書き換え、「死」を克服できたとしても、それはまやかしでしかない。
人間は、「死」を受け入れなければいけないのだ。
だからこの研究は停止するべきだと。
仮にクローンや機械脳、生体転送といったSFの世界でよく見る技術が実現した時にもこの問題は発生する。
まさに「テセウスの船」だ。
人によっては「同一だ」と言うだろう。別の人間は「同一ではない」と言うかもしれない。
その結論が人類の総意として確定しない限り、「同一の存在」を確定させることはできないのだから。
これが、「僕」の結論。
「最初」の「僕」だったらどのような答えを出したのだろうか、とふと思う。
肉体の記憶まで完全にコピーできれば「同一」と言い切るのだろうか。
しかし、「僕」にできるのはここまでだ。
「僕」に法律を変える力も、研究をやめさせる権限もない。
そもそも「死」を克服する研究を国が認めている時点で「僕」に勝ち目はない。
この研究の危うさを主張したところで「国」という圧力に押しつぶされる。
だから、「僕」は望むしかできなかった。
できれば、「人」として――。
「貴方は、どうしたいの?」
突然、アカネが「僕」にそう問いかけた。
思いもよらなかった言葉。そんなことを聞かれても、「僕」には選択肢がない。どうすればいい、と困惑気味にアカネを見ると、彼女は「僕」が答えを出すまで待つつもりだ、と言わんばかりにこちらを見ていた。
暫くの沈黙が続き、夜の闇だけが静かに「僕」たちを見守っている。
長い、とても永い沈黙の後、「僕」は答えを口にした。
「……そう、それが貴方の答えね」
アカネが、ぽつり、と呟く。
そこに否定も肯定もなく、「僕」の答えは本当に正しかったのかと一瞬迷う。否、間違っていてはいけない。
「僕」の答えに何も答えず、アカネはくるりと踵を返した。その行動に面食らうが、次の彼女の言葉で全てを理解した。
「いきなさい。それが貴方の選んだ道なら、私には止める権利がない。でも、少しでも後悔があるのなら、一瞬で全てが絶望に変わるわよ」
そう言って、彼女が歩き出す。
「貴方は貴方よ。『彼』と相容れない存在のね」
もう会うこともないでしょう、という言葉を残し、アカネが墓地を去る。それを見送り、「僕」もタカユキを見た。
「お前……本当に、それでいいのか……?」
「僕」の答えが信じられなかったのか、それとも納得できなかったのか。それでも、「僕」は構わない、と頷いた。
何故なら――。
「僕は、誰が何と言おうとも、僕は『僕』だから。誰が正しいかなんて、最終的には一般人が決めることだけど僕は僕の正しいと思った道を歩く」
「僕」の言葉に、タカユキは「そうか」、と一言だけ呟いた。それ以外、呟くことができなかった。それだけ「僕」の決断は揺るぎのないものだった。
タカユキが少し頭を掻き、それから「僕」の背中を叩いた。
「ほら、行くぞ。いつまでもこんなしみったれた場所にいられるか」
そう言って歩き出す。「僕」も、タカユキについて歩き出した。
「僕」の未来は「僕」が築く。それは誰にも干渉できないし干渉する権利も義務もない。ただ、心のどこかで「これでよかったのか」と迷うのは自分の決断が正しいとも間違っているともアカネに言われなかったからか。間違っている、と言われても「僕」はこの決断を覆すことはなかっただろう。それでも、何か言われたかった。
歩きながら、空を見上げる。無数の星がきらめく夜空に、一縷の希望を寄せる。
自分のこれからの行動は、赦されることなのだろうか。
星々だけが、それを知っているのだろう。
そして、その光が「僕」の背を押す。
「自分の信じる道を迷うことなく歩け」
そう、かつての「僕」に言われた気がした。