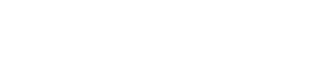魂の所在-The third soul-
これまでのあらすじ(クリックタップで展開)
事故での入院の後、退院した「僕」は退院祝いの飲み会で好みの食べ物について指摘を受ける。
その後の持病の通院で「アカネ」と名乗る医師に出会った「僕」は持病を別の視点からアプローチしたいと言われ、検査を受ける。
しかしアカネのその行動は「主任」に咎められ、何か事情を知っているらしい彼女は病院内へと逃げ込んでしまう。
第3章 呼び起される記憶
しかし、どうするんだよ、とタカユキが問う。
「あいつは何かお前のことを知っているようだった。お前は知りたいと思わないのかよ」
そう言われて、「僕」は考えた。
「僕」はどうしたいのか。
真実は気になる。「僕」のことを何か知っているのなら、聞いてみたい。
だが同時にそれを拒絶する「僕」がいる。
知ってはいけない。知ってしまえば何もかも失う、と。
タカユキは気になって仕方がないようだったが、それでも「僕」に無理強いしようとはせず、
「まぁ、どうしても知るのが怖いってなら無理は言わんが。だが、それでいいのか?」
そう、尋ねてきた。
知りたい。「僕」に何かあるのなら、はっきりさせたい。
それでも、踏み出すことが怖い。
やめろ、知ってはいけない、と「僕」の心が叫んでいる。
知りたい。怖い。
感情がぐるぐると、頭の中を駆け巡る。
このまま諦めれば今までと同じ生活を送ることができるだろう。
それでも、「何かある」と心に抱えたままで、それはできるのか。
そう考えているうちに、「僕」は思わず頷いていた。
知りたい、と。
そうか、とタカユキが頷く。
さっきまで無理強いはしないものの少し強引にどうするか聞いてきていたタカユキは「僕」の決断に「大丈夫か?」と確認してきた。
もう一度、「僕」は頷いた。
知りたい、と。
それに対してタカユキは「分かった」と頷き、自分の考えを口にした。
「ここで引き下がるのをやめたわけだ、多少は無茶するぞ?」
もう一度、「僕」は頷いた。
「だったら言う。あの病院に忍び込む。見つかれば不法侵入、せっかく新社会人になったってのにいきなり
それは覚悟の上だ。
それで今後の行く末が茨の道になったとしても、「僕」は決断した。
知りたい。真実を、全て。
それよりも、タカユキが「僕」に巻き込まれていることが申し訳ない。
「僕」が真実を知るために、いや、何も分からずただ職を失うだけに終わるかもしれないのに付き合ってくれる。
そんなことを言えば「どうせ俺が勝手に気になっただけだ」と笑いそうだが、それでもタカユキは「僕」にとって大切な親友だった。
やると決めた、だからもう逃げたりはしない。
タカユキが周りを見て誰もいないことを確認してから口を開く。
「夜まで待とう。夜に、あの病院に忍び込む。夜ならまだ手薄だろうしあいつらもいないだろ」
その通りだ。夜なら、比較的忍び込みやすいだろう。
タカユキの意見に乗り、「僕」は夜まで待つことにした。
夜の病院は静かで不気味だ。
巡回のナースが不自由しないように最低限の常夜灯だけ点灯した廊下を、「僕」とタカユキは進む。
侵入自体は救急患者用の出入り口から簡単にできた。
トイレに行くふりをしてそのまま奥に進み、暗い病棟に入る。
「僕」とタカユキの足音だけが、廊下に響く。
アカネが消えたと思った角を曲がると、そこから先は「僕」も踏み込んだことがない、知らない場所だった。
幾ばくかの不安を覚えるものの、彼女が何かを知っているというのなら教えてもらいたい、いや、彼女からでなくてもいいから知りたいという気持ちが先に立つ。
「この病院にこんなところがあるなんてな」
歩きながらタカユキが呟く。
それはそうだ、この病院は大学併設のもの、研究施設も設置されているのだろう。
一般外来の病棟とは違い、薄暗い廊下に人の気配はない。「僕」も周りを見回すと、ドアの一つが少し開いていることに気が付いた。それをタカユキに話すと、そこにいるのか、とその部屋に向かって歩き出した。付いて行くと、部屋の奥からカリカリという聞いたことのある音が響いていることに気が付いた。あれは、コンピュータのHDDの書き込み音だ、と思いドアの上の室名プレートを見ると「保管庫」と書かれている。
そろそろと、タカユキを先頭に「僕」は室内に入った。そこには大量のコンピュータ――脳内の知識がこれはスーパーコンピュータだと語りかけてくる――が設置されていた。その熱暴走を未然に防ぐためのエアコンがフル稼働で、なんとなく肌寒い。
「なんだここは……保管庫って書いてる割にはどう見てもサーバルームだろこれ……」
不思議そうな顔をして、タカユキが周りを見る。厳密にはサーバとスーパーコンピュータは違う、と言いたかったがそれは敢えて口にしない。しかし、「保管庫」と書かれているということは何かを保管しているに違いないのだろう。それが何か……「僕」には見当がつかなかった。暫く、二人で何か手がかりになるものがないか探して回る。部屋の中をぐるりと一周するが、結局何も分からない。大抵こういう部屋には情報を引き出す端末があると思っていたがそれすらない。暫く探し回っても無駄足だと判断し、「僕」は部屋を出た。
「何なんだこの部屋……」
そう毒づき、タカユキは薄暗い廊下を見回した。そして、ぎょっとしたように「僕」を見る。
「お、おいお前……」
そう声をかけられて、「僕」は我に返った。
「何だよ、お前、呆然として……何か知ってるのか?」
そうだ。
「僕」は、
ここを知っている……?
初めて来たはずなのに感じる既視感。自分はこの廊下を「運ばれてきた」記憶がある。
それは、自分の中にある記憶と、全くつながりも整合性もない記憶のカケラ。
まさか、と「僕」は呟いた。呟いてから、視線を巡らせ、そこに目的の部屋があったことに気付く。
ゆっくりと、足を運ぶ。膝が笑って、思うように歩けない。タカユキも「僕」の後を追いかけ、その部屋の前に立つ。
そこには、「転写室」と書かれたプレートが掲げられいた。
ここだ、と呟く「僕」の声が廊下に響く。どういうことだ、とタカユキが「僕」を見た。そんなことを聞かれても分からない。ただ、「僕」はここを知っているだけだった。中に何があるのか、この部屋を開けないと分からない。
「僕」の視線がドアの横のタッチパネルに投げられる。そこに表記されていたドアの開閉状況は「開」。厳重な管理が必要なはずのこの部屋の鍵が開いているということは。
いや、あり得ない。
ここにアカネがいて何かしているとは到底思えない。
それでもまるで何かのお膳立てかのようにロックは解除されていて、「僕」を誘っている。
それとも、本当に誰かいるのだろうか。
「僕」はドアノブに手をかけた。ゆっくりと、ドアを開ける。それでも中を見るのが怖くて、目をつぶって部屋の中に踏み込む。数歩入り、タカユキも部屋に入ったことを気配で確認してから「僕」は目を開けた。
「……な……んだ、これ……」
「僕」の後ろで、タカユキがかすれた声で呟く。「僕」も同じだ。部屋の中を一目見ただけで喉がカラカラに乾き、声が出ない。
そこには、様々な機械に接続されたベッドのようなものが設置されていた。
ベッドには、人が寝かされていた。
全身に様々なケーブルが接続され、まるで
そして、その顔は――。
嘘だ、とかすれた声が部屋に響く。
それはタカユキのものだったのか、それとも「僕」のものだったのか。
「どう、いうことだ……」
設備と「僕」を交互に見比べ、タカユキが呟く。
「……お前はここにいるのに……なんでここにも……いるんだ……?」
頭がすっかり混乱してしまい、何を言っているのかタカユキも理解していなかった。それでも、彼の言葉は間違っていない。
そのベッドに寝かされていた人間は、どう見ても、
「僕」
だった。
そっくりさんとかそういうレベルではない。どこからどう見ても、「僕」だった。
よく見ると、わずかに胸が上下して、呼吸をしていることが分かる。
最初に見たときはあまりにも動揺して、アンドロイドに見えてしまっただけだろう。
いや、アンドロイドであるはずがない。
ロボット工学が発展したとはいえ、人間そっくりな、人間と同等の動作をするアンドロイドが開発されたというニュースは聞いたことがない。
いくら世に出ている技術が氷山の一角と言われていても、人間そっくりなアンドロイドが開発されればたちまちネタに飢えているハイエナのようなメディアに取り上げられるだろう。
だから、これはアンドロイドではない、人間だ、と「僕」は自分に言い聞かせる。
でも、どうして。
「僕」はここにいる。
そう、タカユキに聞くと「その通りだ」と肯定した。
「どう考えても、お前はお前じゃないか。ただの空似だろ……?」
そう呟くタカユキの声は相変わらずかすれていた。
その声音に、「まさか」という響きが含まれて行く。
「まさか……クローン……」
そんなことがあるわけない。
アンドロイドと同じように、人間の
クローン技術自体は存在する。でも、それはまだ動物実験の段階で、人間のクローンは倫理的な問題から各国が法律でその研究を禁じている。
その法律の網をかいくぐる、または違法に研究されていることも考えられるだろう。
だが、こんな簡単に侵入できてしまうような施設でクローンの研究を行えば確実に発覚する。
それとも、実は「僕」が知らない間に法律が変わっていた――?
もちろんそんなわけはない。「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」は依然有効だ。そしてだからこそ、クローンではない方法でここに「僕」がいる――。
頭の中の知識が語りかけてくる。だからこそ「僕」がここにいる? どういう意味だ。
「僕」の隣で、タカユキが深呼吸するように大きく息を吐いた。
この部屋に入った時の衝撃をその一呼吸で吹き飛ばし、ベッドの横の端末に目を向ける。
「……流石に、ここまで来たら全部暴かないと気が済まない」
事によってはメディアへのタレコミも考えた方がいい、と呟きながらタカユキは端末に足を向けた。
タカユキが動いたことで「僕」も漸く硬直が解け、後に続く。
ベッドの横に置かれた端末、そう思ったものは専用のコンソールでも何でもなくごく普通のラップトップパソコンだった。
何かのアプリケーションが起動していて、入力待機の状態になっている。
「なんだこれは」
そう言いながら、タカユキがディスプレイに触れる。
ラップトップの周囲に
その判断は正しく、タカユキが振れたことで画面が切り替わる。
「……なんだこれは」
切り替わった画面を見て、タカユキが呟いた。
一見、ファイルアップロードのための
ファイル名は大半が日付となっていた。それも、「僕」が大学に入った頃のものから、比較的最近のものまで、定期的に作成されたかのように、いや、毎月1ファイルずつ並んでいる。
最新の日付は――今日。
その前回、いや、過去に遡った日付に、何故か「僕」の胸がざわつく。
全ての日付が、「僕」の記憶が正しければ「僕」の通院日と一致する。
月に1度、とは言うがイレギュラーで通院した日も、都合が合わずに日程を変えた日も、全てこの一覧にファイルとして表示されている。
偶然だろう、そう思いたいが、あまりにも日付が一致しすぎている。
まさか、という「僕」の声が耳に届く。
知らず、自分の口をついて出たその呟きにタカユキが「僕」を見る。
「心当たりがあるのか?」
頷いて、「僕」は日付のことをタカユキに説明した。
でも、日付は一致しているものの、「僕」の何がデータとなっていて、このエクスプローラに表示されているのかは全く分からない。
それでも、なんとなく分かった。
この端末は「僕」の何かを、「僕」と同じ姿をしたこの人にコピーするものだ、と。
それなら一体何を。
考えようとするが、「僕」の心がそれを拒絶する。
考えてはいけない、今すぐここを離れろ、と心が叫んでいる。
「僕」は何も見ていない、何も考える必要はない、と。
それでも――。
脳内をイメージが駆け巡る。
まただ、と思っている間も様々な数式や模式図、論文が走馬灯のように流れていく。
まるで、「僕」に何かを伝えようとするかのように。
――知っている。
これが何なのか。何をするためのものか。
――いや、「僕」は知らない。
こんなもの、初めて見た。こんなもの、知らない。
――いや、知っている。
何故なら、ここを触れば――。
突然、タカユキが「僕」の腕を掴んだ。
「やめろ、何しようとしてるんだ!」
その声に、我に返る。
「僕」の手は、指は、「転送開始」に触れようとしていた。
心は知ることを拒絶しているはずなのに、体は無意識に答えを開こうとしていた。
「大丈夫か?」
タカユキがそう言ったことで、「僕」は漸く腕を下すことができた。
大丈夫じゃない。この状況で、大丈夫なわけがあるだろうか。
目の前に「僕」と同じ姿の人間がいて、「僕」に関係のありそうな「何か」を転送することができるようになっている。
その「何か」とは。
「まさか……お前、自身……?」
何かに気付いたかのようにタカユキが呟く。
その呟きが部屋に反響する。
「そうだ」
不意に、昼間聞いたアカネが「主任」と呼んだ男の声が響いた。直後、設備の影から姿を現す。
「来ると思っていたよ。アカネがあんな真似をしなければ君は何も知らずにいられたものを」
忌々しそうに主任が口を開く。
「だが、知られてしまったからには、処分せざるを得ないかもな」
「……どう、いうことだ」
「処分」という言葉にタカユキが身構え、主任に向けて問う。
「こいつを、殺す気なのか」
タカユキの言葉に主任はふむ、と顎に手をかけ、それからなるほど、と納得したように頷く。
「用済みの
「な――」
そう、言葉に詰まったタカユキの喉が鳴る。
タカユキが一度「僕」を見て、それから主任に向き直る。
「モルモット、だと? こいつ、が?」
ああ、と主任が頷く。
「彼は我々の研究には必要でね。だがこのことを知ってしまったからには今後の研究に差し障りが出る。ちょうどバックアップも取ったばかりだ、『次』に期待しよう」
「次」という言葉に、「僕」は思わず自分の手を見た。
あの事故の後からずっと感じていた「何かおかしい」という感覚。
――まさか。
――「僕」は。
――「僕」じゃない……?
この時ほど、「僕」は自分の考えを否定してほしいと思ったことはないだろう。
こんな考え、馬鹿げている。
そんなことが、あるわけがない。
あっていい、はずがない。
それなのに、主任は、
「君はいつから自分がオリジナルだと勘違いしていた?」
言葉は違えど、肯定した。
膝から力が抜けるかのような錯覚を覚える。
そのまま床に崩れ落ちかけた「僕」をタカユキが支える。
――嘘だ。
――それじゃあ、「僕」は。
「……オリジナルじゃない、ってことは、まさか、クローン……」
本当に研究していたのか? とタカユキがかすれた声で呟く。
法律で禁止されている人間のクローンを、本当に生み出している……?
クローンか、と主任が呟いた。
「法律が許せばその方が人道的にはなるんだがな。法改正がまだ追いついていないのでね」
――法律が許せば?
「法律が許せばクローンですら作るって言うのかよ! ふざけてんのか!」
――それなら、この人物は。
「そもそも、ここで寝てるのは誰なんだよ。こいつそっくりで、双子か何かなのか?」
いや、「僕」に兄弟はいない。
タカユキもそれは知っているはずだ。
タカユキとはもう長い付き合いで、「僕」に家族がいないことは知っている。
それとも、「僕」が知らない、生き別れの兄弟がいたとでも――。
ふん、と主任が鼻で笑う。
まるで「当たり前のことを聞くな」と言わんばかりに「僕」を見て、
「決まっているだろう、『彼』だよ」
そう、はっきりと言った。
「いつから、『彼』が一人だけだと思い込んでいた?」
おぞましいまでの主任の言葉に眩暈を覚える。
――「僕」は、一人ではない?
しかし主任ははっきりと「法律が許せば」と言った。
つまり、クローンではない。
それなのに、「僕」は一人ではないと言う。
「んなわけあるか! こいつは一人しかいないし今ここにいるのが俺の知ってるこいつだけだ! いくら顔が同じでも間違えるわけが」
「現に今、君は間違えているがな」
タカユキの反論を、主任が冷静に否定する。
「そこにいるのは君が知っている『彼』ではないのだよ」
「な――」
嘘だ、というタカユキの呟きが聞こえる。
「そんなわけが、あるか……別人が俺の友人として接するはずが……」
「その根拠は?」
相変わらず冷静に主任が問う。
それはもちろん、とタカユキが答える。
「こいつは俺とこいつしか知りえないことを知っている。共有した記憶も何もかもが俺の知ってるこいつのものだ。こいつが別人なら元々のこいつの記憶を持っているはずがない」
――その瞬間、パズルのピースがぱちりとはめ込まれた。
記憶。
違う、と「僕」は声を上げた。
――記憶なんてもの、何の根拠にもなりやしない――!
「僕」は思い出し、そして納得した。
「僕」の記憶は「僕」のものではない。
「僕」本来の記憶なんてものは存在しない。
事故以前の記憶は、「僕」ではない別の「僕」が体験、もしくは転写された記憶なのだ。
この部屋のプレートの「転写室」という文字の意味は、「以前の僕」の記憶を「今の僕」に移すためのもの。
ファイルに「僕」の通院日に合致した日付が設定されていることを考えると、いや、考えたくないがこのファイルは――「バックアップ」。
「僕」の記憶そのもの、だろう。
「僕」には脳に疾患があって、その経過観察のために通院していると思っていたが、そんなことは実際にはなく、ただ記憶を抽出してバックアップするためだけの、通院。
記憶の抽出なんて、脳内の情報を抜き取るなんて馬鹿馬鹿しい、そう思うものの何故か体は納得する。
記憶の抽出自体は、技術として完成しつつあるのだと。
そう思ってから、「僕」はベッドの上を見た。
多分、今ここで眠っている「僕」そっくりの人間が次の「僕」なのだろう。
主任は今日、「僕」がここに来るのを見越して、次の「僕」を用意した。
今ここにいる「僕」をなかったことにして。
主任が「分かっているじゃないか」と頷く。
「そういえば、タカユキ……と言ったか。アカネから聞いたが君は彼女と都市伝説の話をしたようだな。そうだ、その都市伝説は事実。この研究施設ではヒトの記憶をコンピュータに抽出し、別の個体に転写する技術を研究している。『生命の再生』と都市伝説では伝えられているけど、概ね間違ってはいないな」
「その被験体がこいつだというのか!」
主任が、小さく頷く。
「『彼』は自ら望んでこの研究に同意した。『死』の概念を覆すために」
「死」の概念を覆す……? それは、生物が「死」から解き放たれる、ということなのか?
それは危険だ、と「僕」は思った。確かに、記憶を転写すれば肉体が朽ちても新たな肉体で「蘇る」ことは可能だろう。
しかし、それでいいのか?「死」という概念を消去して、本当にそれでいいのだろうか。
そんなことがあっていいはずがない。ヒトは、生物として「死」を受け入れなければいけない。それを受け入れないのは神に対する叛逆だ。
「……そうか、君はそう言うか」
「僕」の主張に、主任はそう呟いた。
そこに少しばかりの寂しさを感じたような気がしたが、それでも主任に同意してはいけない。
その頃になって、「僕」は漸く膝の力が戻り自分の足で立ち上がった。
まっすぐ、主任を見る。
違うのか、と主任が「僕」を見る。
「『彼』はそんなこと言わない。『死』を克服することこそが人類が進むべき道だと言っていた」
嘘だ、そんなことを「僕」が言うはずがない。何かの間違いなのではないのか。
だが、その考えの裏でまた知識が語りかけてくる。
その通りだ。人類はあらゆる障害を科学で乗り越えてきた。ならあらゆる人類の未来に待ち受ける「死」という障害を克服しなければならないのは自明の事だ――。
主任が、言葉を続ける。
「やはり、記憶転写はまだ研究段階だというのか。いや、記憶転写はできてもベースの人格が同調しない、ということなのか。これは君の脳を詳しく調べる必要があるな」
ぞくり、と背筋を冷たいものがはしる。同時に、「僕」は理解していた。やはり、いつもの検査は嘘で記憶のバックアップを取っていたのだと。さらにあの事故で元々の「僕」は死んでいて、この施設で記憶を転写し、何事もなかったかのように世に放ったのだ、と。
「僕」の脳を調べる、それなら普段から記憶のバックアップと同時に確認しているのではないのか。主任が「敢えて」言うということは―― 。
「僕」の考えが伝わったのか、主任が一歩こちらに歩み寄る。
「処分とは言ったが、ただ処分するだけではもったいない。今後のために解剖でもしないと……」
「何をバカな!」
「僕」達の会話を聞いていたタカユキが叫んだ。
「こいつはこいつだろ! お前らの実験で思い通りの結果にならなかったからと言って殺すのか?これが公になれば――」
「このプロジェクトは国が認めている。人類が『死』を克服できるのなら多少の犠牲は厭わん、とな」
「な――」
国に認められている、だから被検体である「僕」の命はどのように扱ってもいい、ということなのか。そんな人道に背いたことを、国が認めるとは……
「どうせ失敗作だ。それに君の代わりはいくらでもいる」
ぐるりと設備を見回し、主任が言った。さっき抽出した記憶を受け継いだ次の君が何事もなかったかのように社会に戻るのだ、と。
「しかし、そうは言っても『次』はここにいるとしてもその次が必要になった場合、どうするんだ。クローンじゃない、と考えるなら――」
タカユキが思わず尋ねる。
勿論、今の「僕」を死なせるわけにはいかない。だが、簡単に被検体を殺せるほど「僕」にストックがあるとも思えない。
クローンではないという以上、何かしらの手段で「僕」の代わりを用意することになるがそれはどうやって。
よく考えろ、と「僕」は自分に言い聞かせた。
主任の言葉から、真意を推測しろ。
「次」はあったとしても「その次」はない。
ただのブラフの可能性は高い。
それでも、ブラフという確証はない。
「次の僕」を研究所に閉じ込める? いや、そんなことを行うはずがない。
「今の僕」が社会に出ていたことを考え、さらに「国が認めたプロジェクト」ということを考えると「記憶転写された僕」が社会に出るのは一つのモデルケースとしてのはず。
社会生活を送ることへの影響を調査していたのなら研究所に閉じ込めることはない。
それにただの記憶転写実験だけなら被検体を生かし続けることもましてや不安要素の多い社会に送り出すこともないはず。
――何がある。
クローンでもない、隔離もない。次を調達することができる。
――まさか。
いや、そんなことありえない。あり得るはずがない。
そんなことがあっていいはずがない。
「僕」が本当に別人なんて、考えるだけでもおぞましい。
しかし、それでも納得できるのだ。主任の言葉が。
「人道的になる」ということは、つまり――。
「金のために自分の命を売る人間なんてごまんといるんだよ、今の世の中」
「僕」もタカユキも声が出なかった。いや、出せなかった。
――国は、人身売買ですら認めているというのか――。
そういうことなのだろう。家族か何か理由があり、金銭が必要な人間が自分の命と引き換えに幾ばくかの金を得る、そして全てを――「自分が存在したという証」全てを奪われ、「僕」として再生されるのだ。
体格さえある程度合えば顔など整形でいくらでも変えられる。
だから親友のタカユキですら騙されたのだ、と。
それなのに。
タカユキは「僕」を庇うように前に立った。
片手で「僕」を制するように、そして主任を睨みつける。
「『彼』を渡したまえ。君には何の関係もない赤の他人だ」
主任が「僕」に向け、片手を差し出しながら言う。
「僕」にはもう何もないのだと。
そう言わんばかりの顔で、タカユキにどけと要求する。
「ふざけんな! お前は別人というかもしれないが! こいつは俺の友人だ! 今も昔も変わりない!」
だからお前になんか渡さない、とタカユキは「僕」の腕を掴んで走り出した。
部屋を出てしまえば、もしかすると逃げられるかもしれない。
しかし、部屋の出口は主任の方が近く、「僕」は明らかに袋の鼠だった。万事休す、ここまでなのか、とタカユキも思ったその時。
「逃げて!」
突如、アカネの声が響いた。同時に「僕」と主任の間に何か赤いものが飛来し、直後、辺りがまっ白い煙に包まれる。
「な……消火器 !? 」
消火器が吐き出した消火剤で視界が閉ざされ、その場にいた全員がうろたえる。「僕」もその例に漏れなかったが、すぐに腕を掴まれる。
「こっちよ!」
アカネに腕を掴まれ、「僕」はタカユキの姿を探した。腕は掴まれていたがそれでも姿が見えないだけで不安になる。
「大丈夫だ、俺はここにいる」
すぐ横でタカユキの声が聞こえ、「僕」は誰にも見えていないのに頷いた。
主任が「僕」を探すが、捕まる前になんとか部屋を飛び出す。そのままアカネに連れられ、「僕」は病院を、いや、研究所を脱出した。